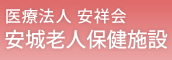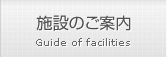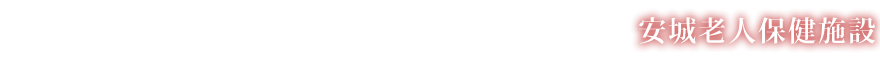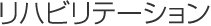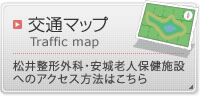こころと身体を活かす工夫をご提案します
身体機能や認知機能の問題により今までの生活の維持が困難な方が、入所・通所サービスを利用されています。
その方のもつ能力を活かし、その人らしく・明るく・楽しく生活できるように、生活リハビリを主体とした様々な手段により、
動作の改善・介助量の軽減・QOL(生活の質)の向上を図れるように支援します。
当施設リハビリテーションの特徴
理学療法士(PT)6名、作業療法士(OT)7名、言語聴覚士(ST)2名の合計15名の常勤・非常勤のリハビリ専門職が在籍し、リハビリテーションを行っています。
1人の利用者様に1人の療法士が担当としてつきますが、各職種の専門性を活かし、チームとして支援できるように努めています。
在宅復帰・在宅生活の維持が目的の方には、日常生活活動訓練・福祉用具や住宅改修のアドバイス・家族指導・訪問指導など必要に応じて幅広く対応するように心がけています。
入所リハビリテーションの内容
在宅復帰の実現やより良い施設生活の継続のため、日常のケアに加えて運動機能(関節の動きや筋力など)訓練・基本動作(寝返り・起き上がり・起立・歩行など)訓練・日常生活活動(食事・排泄・更衣・入浴など)訓練・環境整備など、利用者様の状態や状況に合わせて様々なリハビリを提案・実施しています。
新規の利用者様には、短期集中リハビリテーション(入所日から起算して3か月間、週6回を上限とする)や認知症短期集中リハビリテーション(入所日から起算して3か月間、週3回を上限とする・規定から外れる方を除く)をお勧めすることで、利用者様の運動機能や認知機能の回復を集中的に促し、その人らしい生活が1日も早く実現できるよう努めています。
定期的にサービス担当者会議を行い、介護士や看護師など他職種からの情報を収集することで、利用者様お一人お一人に適したリハビリテーションの計画を立案しています。
入所・ショートステイのリハビリテーション風景
歩行練習

階段昇降練習

起き上がり練習

認知機能訓練(計算・書き取り・間違い探し)

認知機能訓練(趣味を活かした刺し子)

STによる摂食・嚥下評価

STによる言語訓練

ショートステイのリハビリテーションの内容
在宅生活をより充実できるようリハビリを行っています。リハビリ専門職による個別リハビリのご希望の有無に関わらず、3ヵ月ごとに評価を行い、生活改善のためのご提案をさせていただきます。
通所リハビリテーションの内容(要介護)
【1】リハビリテーション会議の実施
定期的にリハビリテーション会議を行い、リハビリテーション計画書の見直しを行います。
利用者様、ご家族、医師、専門職等、利用者様に関わる事業者で情報共有します。

【2】利用者様の状態に沿ったリハビリテーションの提供(PT、OT、ST)
個別リハビリテーション
リハビリテーション計画書を基に利用者様の在宅生活を継続できるようリハビリテーションを行います。
短期集中リハビリテーション<退院(所)または認定日から起算して3か月以内>
身体機能と基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させるため、利用者様の状態に応じて、退院・退所直後に
集中的なリハビリテーションを個別に行います。
生活行為向上リハビリテーション<利用開始月から起算して6か月以内>
加齢や閉じこもり、活動性の低下による廃用症候群などにより、生活機能の内、活動する能力が低下した
利用者様に対して、活動機能を向上できるよう具体的に目標を立て、実施計画に沿ったリハビリテーションを行います。
認知症短期集中リハビリ加算Ⅰ<退院(所)または通所開始日から起算して3か月以内>
認知症と診断された利用者様の認知機能や生活環境等を踏まえ、
応用的動作能力や社会適応能力(生活環境または家庭環境へ適応する能力)を最大限に活かしながら、
当該利用者様の生活機能を改善するためのリハビリテーションを行います。
介護予防通所リハビリテーションの内容
住み慣れた自宅で自分らしく生き生きとした生活をこれからも送れるように、
利用者様自身が目的・意欲を持ってリハビリに取り組めるように専門職が支援します。
リハビリの流れ
【1】事前アセスメント
[A]体力測定
[B]リスク評価
(現病歴、既往歴、血圧、服薬状況、痛みなどを確認します)
[C]認知機能評価
☆[A・B]3ヵ月に1回実施 [C]6ヵ月に1回実施

血圧測定と運動の記録
【2】ケアプランとアセスメントを基に運動機能向上計画を立案
【3】計画に基づいてリハビリ実施
☆自主トレがメインですが、利用者様の身体状況、認知機能に応じてサポートします。
☆リハビリ後は、利用者様自身で血圧測定・運動等の実施状況を記録することで見当識や記憶の保持にもつながります。
通所リハビリ(要介護・要支援)風景
歩行訓練


階段昇降訓練

屋外歩行訓練

関節可動域訓練

自転車エルゴメーター

STによる言語訓練

認知機能訓練(塗り絵、計算、脳トレなど)

STによる嚥下、摂食評価・訓練

作業活動(日常生活で実際に必要な活動)